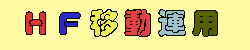移動運用をするための足踏み基台やポールも車に積んでいますが、家族との 行楽のついでに実施するには少し大袈裟すぎるように感じていました。
特に50MHzとなると、場所の選定とともに車載の2エレHB9CVを 組み立てる時間もかかり、持って行っても使わないことがほとんどでした。
そこで、手軽なHFの運用を目指し、移動用の釣竿ベースを作ってみました。
車を換えたため、画像を入れ替えました。(1998年10月)
 1. 車の牽引フックへの取り付け金具は、ICOMのAH−2b用を使いました。 ('98.10.25) 1. 車の牽引フックへの取り付け金具は、ICOMのAH−2b用を使いました。 ('98.10.25)
 2. 後方へ伸びるパイプは、AH−2b用のパイプが短すぎたためにあきらめ、 少し入れにくい状況でしたが、矢崎のイレクタ(32Φ × 40cm)を 押し込んでいます。('98.10.25) 2. 後方へ伸びるパイプは、AH−2b用のパイプが短すぎたためにあきらめ、 少し入れにくい状況でしたが、矢崎のイレクタ(32Φ × 40cm)を 押し込んでいます。('98.10.25)
 3. 垂直のパイプはお馴染みの排水管(VU40 内径44mm 約45cm長)を使い、 水平部と垂直部を止めているのは、グラスファイバー工研のデベマウント (52 X 32 mm)です。('98.10.25) 3. 垂直のパイプはお馴染みの排水管(VU40 内径44mm 約45cm長)を使い、 水平部と垂直部を止めているのは、グラスファイバー工研のデベマウント (52 X 32 mm)です。('98.10.25)
 4. 以前は、下部(上記3の取り付け部)だけで固定していましたが、風が強くなると 釣竿がゆれ、強風で倒れる事を心配していましたが、ルーフレール部に固定する 器具をつくり固定できるようにしました。('98.10.25) 4. 以前は、下部(上記3の取り付け部)だけで固定していましたが、風が強くなると 釣竿がゆれ、強風で倒れる事を心配していましたが、ルーフレール部に固定する 器具をつくり固定できるようにしました。('98.10.25)
 5. 違う角度からの画像です。11月以降はこの装備で移動運用する予定です。('98.10.25) 5. 違う角度からの画像です。11月以降はこの装備で移動運用する予定です。('98.10.25)
 6. 配水管の下部は5mmの穴を4個空け、挿入する釣竿が落ちないよう に結束バンド2本で十字に止めています。('98.10.25) 6. 配水管の下部は5mmの穴を4個空け、挿入する釣竿が落ちないよう に結束バンド2本で十字に止めています。('98.10.25)
最近、結束バンド部を切り取り、ただのパイプとして使っています。釣竿を地表面で支えたほうが安定するため、変更しました。(追記:2000.5.06)
 7. 送水管(VP13)を使い組み立てました。短いほうが2本の折りたたみで長いほうが 3本になっています。パイプ1本の長さは総て約50cmで、片側に継ぎ手を 固定して専用の接着剤で止めています。 キャンプ用のパイプを思い出し、全体を継ぎ足して、最後に中に通した紐を引く ことで、固定します。取り付けやすさとコンパクト収納を可能にしています。 7. 送水管(VP13)を使い組み立てました。短いほうが2本の折りたたみで長いほうが 3本になっています。パイプ1本の長さは総て約50cmで、片側に継ぎ手を 固定して専用の接着剤で止めています。 キャンプ用のパイプを思い出し、全体を継ぎ足して、最後に中に通した紐を引く ことで、固定します。取り付けやすさとコンパクト収納を可能にしています。
工夫:送水管は専用の継手でつなぎますが、そのままでは継手の中央付近まで差し込めません。 そこで、送水管の先(両側)をガスこんろであぶり、少し柔らかくなったところで、 継手をシゴクようにしながら奥まで差し込むと、中央までスムーズに挿入できるように なります。('98.10.25)
以前の装備
|